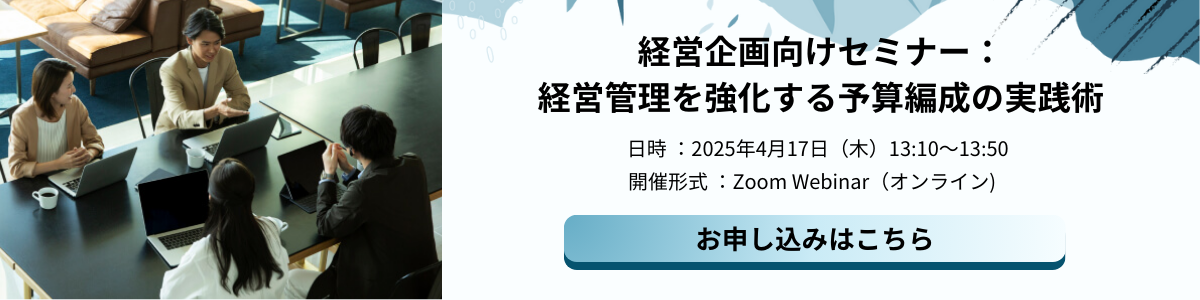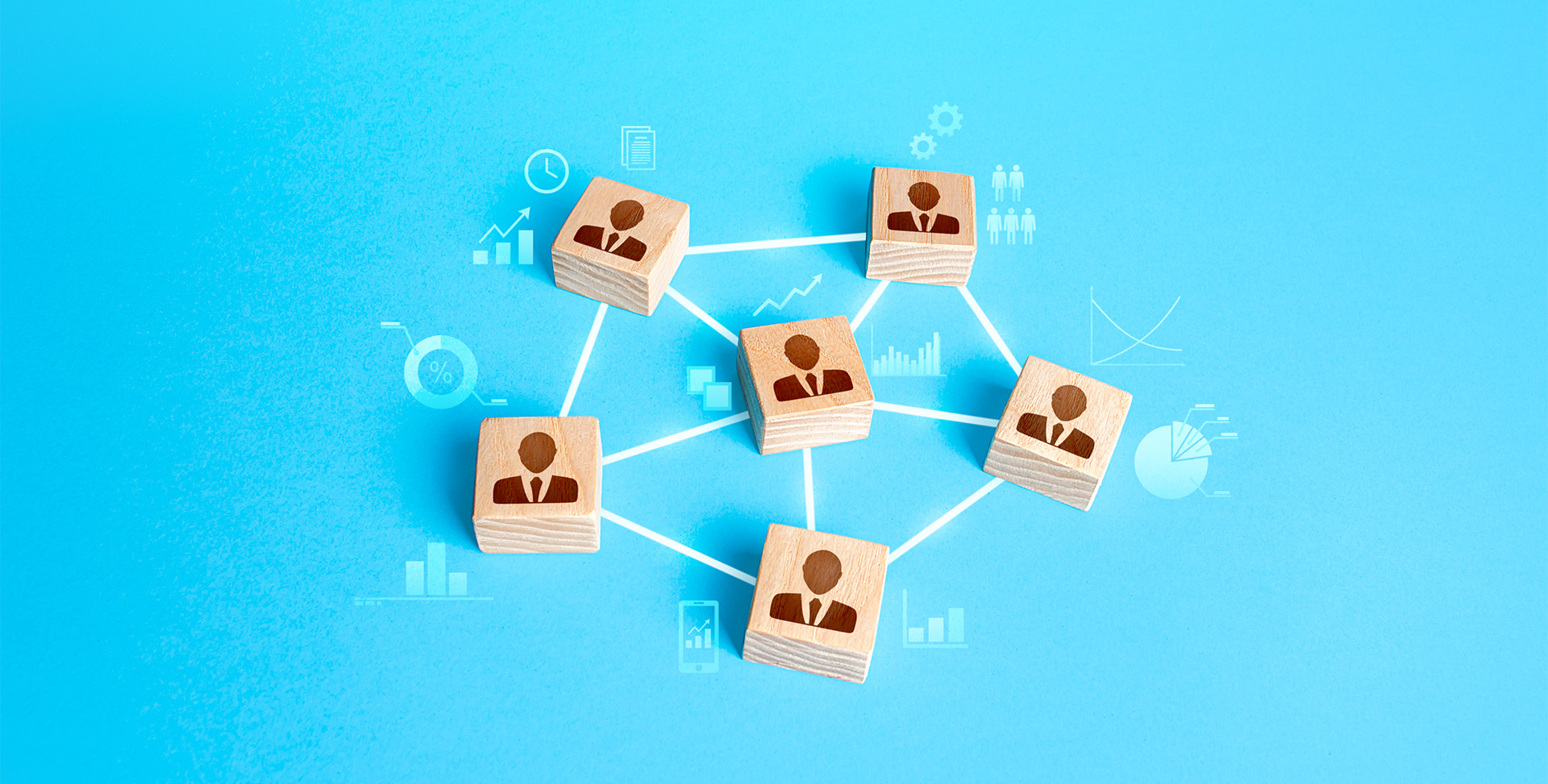近年、企業において法令違反や情報漏えいなどの問題が発覚すると、すぐにコンプライアンス強化の必要性が叫ばれます。この記事では、コンプライアンスの意味や重要性、強化に向けた具体的な取り組みについてまとめました。また、違反事例や似た言葉との定義の違いについても解説していますので、コンプライアンスを遵守し、健全な企業経営を実現するためにお役立てください。

コンプライアンスとは?
事業活動を行っていくうえで、「コンプライアンス」の意味や役割を適切に理解することが重要です。コンプライアンス違反が起これば、企業継続の危機にもつながる恐れがあります。ここではコンプライアンスの定義や類似する言葉との違いについて取りあげます。
コンプライアンスの意味
コンプライアンスとは、日本語で「法令遵守」を意味します。ただし、実際には法令に加えて、企業倫理や社会的規範の遵守を含む広義の概念です。社会的信用を維持するためにも、企業にはコンプライアンスの遵守が求められます。
コンプライアンスは、法令の遵守に加え、企業倫理や社会規範の遵守を含む概念であり、企業が社会的責任を果たしながら持続的に成長するための基盤となる考え方です。従業員全員で企業倫理や社会倫理を含めた守るべきルールを意識する姿勢を持つことが重要です。
CSR(企業の社会的責任)と関係性
コンプライアンスとよく似た言葉に「CSR(Corporate Social Responsibility)」があります。これは「企業の社会的責任」という意味の言葉です。企業は、規模が大きければ大きいほど社会的な影響力や発言力も大きくなります。企業には環境保護や労働環境の改善など、多様な取り組みを行い、社会的責任を果たす姿勢が求められています。
構造としては、CSRは企業が社会的責任を果たすための概念であり、その一環としてコンプライアンスが含まれます。そのため「社会貢献を実施していく」という広義の意味では、CSRもコンプライアンスも同じです。狭義では、CSRの取り組みのひとつとしてコンプライアンス精神があると考えられます。したがって、両者は別のものであり「コンプライアンス=CSR」と誤解しないようにしましょう。
コンプライアンスに似た言葉と意味の違い
CSRのほかにも、コンプライアンスと混同しやすい言葉があります。たとえば、「コーポレートガバナンス・内部統制・リスクマネジメント」は意味が似ていますが、企業経営において異なる役割を持ちます。それぞれの言葉の定義や役割について解説します。
コーポレートガバナンスとの違い
コーポレートガバナンスは、日本語で「企業統治」を指します。コーポレートガバナンスとは、企業のステークホルダーが経営者の利己的な判断がないか監視・牽制し、経営をコントロールする考え方です。
コンプライアンスは法令遵守、コーポレートガバナンスは企業統治であり、両者は異なる概念です。コーポレートガバナンスが経営をコントロールしていれば、コンプライアンスも保たれます。コーポレートガバナンスは、企業を適切に統治・管理する仕組みを指し、その適正な運用がコンプライアンスの実現を促進する要素のひとつです。
内部統制との違い
内部統制とは、企業の経営目標を達成するためのシステムを指します。金融庁が示す「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」によると、内部統制には以下の目的があります。
- 業務の有効性および効率性
- 財務報告の信頼性
- 事業活動に関わる法律等の遵守
- 資産の保全
加えて、内部統制を構成する要素は6つです。
- 統制環境
- リスクの評価と対応
- 統制活動
- 情報と伝達
- モニタリング(監視活動)
- IT(情報技術)への対応
内部統制はコンプライアンスの一環であり、適切に機能することで法令遵守を含む健全な経営体制の維持につながります。
参照元:金融庁|財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について
リスクマネジメントとの違い
企業の経営活動や社会的活動では、さまざまなリスクが存在します。リスクマネジメントとは、そのようなあらゆるリスクを想定して、それが起こらない回避方法を設定、またはリスクが発生しても最小限に抑える管理方法です。リスクマネジメントでは、法令違反のリスクも管理対象です。この点ではコンプライアンスと似ています。
コンプライアンスは法令遵守をはじめ、社内規則や社会規範などまで守る概念です。他方で、リスクマネジメントは企業がコンプライアンス違反しないよう、コンプライアンスにおけるリスクを想定しながら企業を管理することを意味します。
企業がコンプライアンスを重視するようになった背景
コンプライアンスが企業経営において一般的となったのには、以下のような歴史的な理由や背景があります。
規制緩和による企業の責任の増大
日本では、1980年代後半から1990年代にかけて、大幅な「規制緩和」が実施されました。規制緩和は、日本政府が実施した経済政策のひとつで、民間企業が自由に事業競争するにあたって、それまで実施されていた規制を緩和する動きになります。結果として国内には大小さまざまな企業が乱立し、実際に日本の経済成長につながったといえるでしょう。しかし、自由な競争ができるようになった反面で、企業には自由と引き換えに重大な責任も伴うようになりました。
企業の不正行為や法令違反の増加
コンプライアンスという概念が重視されるようになったのは、企業の不正行為や法令違反などの事件が相次いだという背景も関係しています。
わかりやすいケースを挙げると、企業の食品偽装問題があります。2007年には有名メーカーが賞味期限切れの食品を販売していたことが発覚、そのほか産地を偽装するなど、食品偽装問題は頻繁に取り上げられる不正行為のひとつです。
また近年、個人情報保護の意識が高まる中で、企業の個人情報流出の問題も見逃せません。2004年には、通信系の企業で400万件以上の顧客データ流出が明らかになりました。この事件には従業員が関わったとして非常に問題視され、企業が信用を失うきっかけになったのはいうまでもありません。
法令やモラルのあり方の変化
社会全体の環境や価値観の変化が、コンプライアンス精神重視の考え方に影響を与えている部分もあります。
たとえば、2006年には会社法が改正されたことにより、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の企業は、コンプライアンス重視の業務体制を整備することが法律的に義務付けられました。また、同年には公益通報者保護法という新しい法律が施行され、これによって内部告発を行った従業員の権利は強固に守られるようになり、不当な解雇などがあった際には、企業は厳しく罰せられるようになりました。
今からでも企業がコンプライアンスに取り組むべき理由
先述のコンプライアンス重視が浸透した背景も影響して、現在多くの日本企業ではコンプライアンスに取り組んでいます。しかし、一部企業ではまだ取り組めていない、または取り組みが不十分とされています。コンプライアンスに取り組んでいない企業は、取り組むべき理由を理解し、制度の整備や意識改革を行っていく必要があります。
CSR実現のため
取り組むべき理由のひとつとして、CSR(企業の社会的責任)を果たすには、コンプライアンス遵守が欠かせないことが挙げられます。企業や従業員がコンプライアンス違反を行い発覚した場合、企業は社会的信頼の失墜から、信用度や企業価値が下がる恐れがあります。
コンプライアンス違反の原因は、企業や従業員の社会に対する責任感の欠如が大半です。コンプライアンス違反を行うと、同時にCSRも果たしていないことになります。よって、「コンプライアンスを遵守しているのか」という視点がCSR実現に大きく影響します。
ESGの重要性が高まっているため
現在、国際的にESGの重要性が高まっていることも理由のひとつです。ESGとは、以下の3つの頭文字です。
- 環境(Environment)
- 社会(Social)
- ガバナンス(Governance)
このESG経営に取り組んでいる企業が投資対象として評価されています(ESG投資)。企業が安定した資金調達により成長し続けるには、コンプライアンスを整えて、ESGへの配慮ができていることを示さなければなりません。
ESG要素が不安視されると、投資家は企業を投資対象に選ばなくなってしまいます。そのため、ESG経営が推進できるコンプライアンスの整備と遵守が重要です。
あらゆるリスク管理が必要なため
インターネット、特にSNSの普及により、現在は企業で問題が生じるとすぐに拡散され「炎上」するようになりました。炎上するとブランドイメージの毀損だけではなく、事業活動の停止や廃業にまで発展してしまう可能性もあります。情報化社会の中で、一度コンプライアンス違反が発覚し社会的信用を損ねると、企業イメージを回復するのは困難です。
また、現在は環境や社会問題へのリスクや、グローバル市場に進出する際のリスクなど新たなリスクが生まれています。これらのことから、企業の持続的な成長やリスク管理の一環として、変化に対応したコンプライアンス強化が必要とされているのです。
コンプライアンス違反となる事例
法令を理解し健全な企業経営が行えるコンプライアンスを作成しなければなりません。加えて、周知徹底の際には従業員に向けてどのような行為が違反とみなされるのか尺度や他企業の事例を示す必要があります。このコンプライアンスに反する行為にはさまざまな種類があり、なかには、刑事罰の対象となる違反行為もあります。
法令違反
企業で起こる法令違反には、景品表示法違反や食品衛生法違反、不正競争防止法違反などがあります。具体的には以下のような事例が起こりやすいと考えられます。
- 景品表示法違反:データを提示しない広告、誇大広告
- 食品衛生法違反:不衛生な環境での食品の製造や提供
- 不正競争防止法違反:産地、消費期限などの偽装表示
- 著作権法違反:イラストレーターのイラストなどの著作物を自社商品などに無断で使用する
- 入札談合等関与行為防止法、独占禁止法違反:談合など
- 金融商品取引法違反:インサイダー取引など
法令違反は社会に与える影響が大きく、特に信頼失墜につながりやすいため、注意が必要です。
労働問題
労働に関するコンプライアンス違反は、例を挙げると「長時間労働を強いる」といったケースです。残業代未払いの場合、訴えられて裁判となるケースもあります。また企業側は正当な解雇だと思っていても、不当解雇として訴えられるケースもあります。
そのほかに労働問題で起こるコンプライアンス違反は、パワーハラスメント・セクシャルハラスメント(黙認も含む)、不法就労の外国人の雇用や雇用のあっせん(入管法違反)、募集時の年齢制限(労働施策総合推進法違反)などです。
不正会計
コンプライアンスが注目されるようになったのは、アメリカの大手企業で不正会計が発覚したことがきっかけです。日本でも大手企業などで粉飾決算が度々起こっており、社長など経営陣が逮捕された事件もありました。不正会計による企業の倒産は現在でも起こっています。
不正会計にはさまざまな方法があり、横領や会計・経営に関する書類の改ざんなどを故意に行うことを指します。粉飾決算は不正会計の一種で、財務諸表の改ざんや架空計上などで、経営状況を実際よりも良好に見せかける手法です。不正会計が発覚すれば、複数の刑事罰や民事責任が生じます。
情報漏えい
従業員の情報セキュリティに関する意識の低さが原因で情報漏えいしてしまい、顧客の個人情報などが流出することもあります。たとえば、従業員が顧客情報の入ったパソコンやUSBを社外に持ち出し紛失するケースです。リモートワークが浸透している現在は、社外での情報漏えいには特に注意が必要です。
また、企業がサイバー攻撃を受け情報漏えいしてしまうケースも見られます。情報漏えいが起こると、企業の社会的信用が失墜し企業経営に多大な影響をもたらします。経営危機に陥る恐れもあるため、セキュリティ対策や情報リテラシーの改善施策などをしっかり行わなければなりません。
コンプライアンス遵守の企業になるための具体策
企業は、コンプライアンス遵守のために、以下のような取り組みを実施していく必要があります。コンプライアンス精神を育てていくための具体的なプロセスとして、自社に合った取り組みを考える際にぜひ参考にしてみてください。
企業の基本方針・行動規範の策定と周知を行う
コンプライアンス違反になり得るリスクを洗い出し、リスク管理を反映させたうえで、基本的な方針や行動規範を策定します。従業員によって規範や価値観が異なるため、ヒアリングを実施し、参考にするのもおすすめです。
基本方針・行動規範を作成したら、公開する前に弁護士へ監修を依頼し、法令に違反しないか確認します。そして基本方針・行動規範が定まったら、従業員への周知徹底が必要です。全従業員へのメールなどでの通知はもちろん、社内での掲示や、経営陣が率先してコンプライアンス遵守する姿勢を見せるのも効果的です。
従業員向けの相談窓口を作る
内部告発によって不正行為が発覚するケースは少なくありません。また、近年に社会問題となっている各種ハラスメントについても相談しやすいよう、相談窓口の設置は非常に重要です。不正や不祥事による影響が拡大する前に、事態を収束できる場合もあります。従業員向けの相談窓口を設ける際には、匿名性を守るなど、相談しやすい環境を整えることが大切です。
コンプライアンス研修を定期的に行う
経営陣のみがコンプライアンス遵守の精神を理解していても、社内全体にその考え方はなかなか広まりません。定期的に研修やセミナーを実施し、従業員一人ひとりの意識向上を図るきっかけを作る具体的な取り組みを心がける必要があります。
コンプライアンスマニュアルを整備する
コンプライアンスマニュアルをあらかじめ整備しておくことも重要です。マニュアルがあればそれぞれの判断にゆだねることなく、何が不正にあたるのか明確に理解できます。
また、コンプライアンス違反があった場合、どのような罰則があるのかもマニュアルには具体的に示しておきましょう。コンプライアンス違反がどれだけ重いことなのか、罰則とともに示しておくことで、理解するきっかけが作れます。
まとめ
コンプライアンスに反する行為が発覚すると、企業のブランドイメージや社会的信用の失墜、人材流出、加えて労務トラブルや裁判、場合によっては刑事罰が科されるといったあらゆる可能性が考えられます。
このような事態を招くことがないよう、自社に合わせたコンプライアンス強化の施策を講じていく必要があります。この機会にコンプライアンス管理体制チェックシートを活用して、自社の状況把握を進めてみてはいかがでしょうか。現状を洗い出すことで、必要な施策が見えてくるはずです。
- カテゴリ:
- ガバナンス/リスク管理